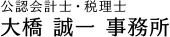1.推計課税が許容される趣旨
所得税法及び法人税法においては、納税者に帳簿書類の備付け、記録及び保存を義務付け、他方、青色申告者には課税手続や税額計算等に関する各種の特典を付与するなどして、帳簿書類という直接資料に基づく所得金額の算定、すなわち「実額課税」を可能とする納税環境の整備を図っています。
しかしながら、現実には、帳簿書類の備付け等をしていない納税者、帳簿書類の内容が不備・不正確で信頼できない納税者、そして、帳簿書類の提示を拒むなど調査に非協力的な納税者も存在します。
このような納税者に対して「実額課税」することは不可能ですが、直接資料が入手できないからといって課税を放棄することは、公平負担の観点から適当ではなく、ここに「推計課税」が認められる趣旨が見出せると金子宏先生は「租税法」の中で述べられています。
2.推計の合理性
推計課税は実額を把握する資料がないときにやむを得ず間接資料により所得を推計するものですから、推計の方法は最もよく実際の所得に近似した数値を算出し得る合理的なものでなければなりません。
推計の方法が合理的であるというためには、敷衍すれば、次の3点が充足されなければなりません。
・推計方法として当該事案にとって最適な方法が選択されていること(推計方法の最適性)
・推計の起訴事実(数値)が正確に把握されていること(推計基礎の正確性)
・推計方法自体が具体的に真実の所得にできるだけ近似した数値が算出され得るような客観的なものであること(推計方法の客観性)
とりわけ、論点となるのが「推計基礎の正確性(いわゆる推計の柱)」であり、実務上は次のような手法があるようです。
・比率法(本人比率法・同業者比率法)
・効率法(比率法との併用)
・資産負債増減法
実際には、その納税者について実額で掴めた数値に対して、所得率・原価率などについて同業者比率法を用いて所得を推計する事案が大方を占めます。
課税庁には、調査対象の納税者と同業の他社の申告資料が蓄積されており、上記の同業者比率法の推計基礎を求めることは容易であるような印象があるかもしれませんが、現実問題としては、次のような制約が立ちはだかることがあります。
・調査対象の納税者とほぼ同じ事業を営む納税者が検出できるか?
→ニッチな事業・最近新興した事業である場合はどうするか?
・同業他社の規模が調査対象の納税者のそれと乖離していないか?
→いわゆる「倍半基準」の範囲内か?
・同業他社と地域性や件数は推計基礎として十分か?
→存在するにしても1~2社ではその同業他社の個性が捨象されないのではないか?
・過去数年分を遡って課税する場合、同業他社もその年分を青色申告で継続して申告しているか?
私が国税不服審判所において担当した事案についても、上記のような考慮から課税庁が所得税の推計課税を断念したものがありました。
3.実額主張
原処分の適否を審理する行政庁(再調査審理庁・国税不服審判所)が嫌がる主張が「実額主張」です。
上記のとおり、推計課税は実額課税が不可能である場合の代替手段であり、実額計算をするに足る証拠の提供があれば、推計課税の基礎を欠くことになります(これを「実額は推計を破る」といいます)。
納税者が実額主張をするに当たっては、納税者から次の3点を立証する必要がありますが、その帳簿や証憑書類が大量に存在する場合、推計課税を離脱して実額課税に拠ることができるか否かの検証が審理庁にとって大きな負担となります。
・その主張する収入金額が全ての取引先からの全ての取引についての捕捉漏れのない総収入金額であること
・その収入と対応する必要経費が実際に支出されたこと
・事業関連性につき、直接費用については収入との個別的対応の事実、間接費用については期間対応の事実
担当審判官に推計課税事案が配付されると周囲から同情されることがありますが、とりわけ「実額主張」があった場合に力業になることが往々にしてあるからです。