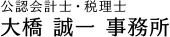1.各地域審判所による裁決書の個性
裁決書は、その全てが「国税不服審判所長(本部所長)」名で出され、それは、行政判断の全国統一性の要請に基づくものですが、実際には、各地域審判所の首席審判官の出身・経験に基づく個性が顕れます。
私が在籍していた大阪国税不服審判所においても、本部所長から裁決権が委任されている所長の人事異動によって、裁決書の個性が大きく変わったことがあります。
2.裁決書が相対的に長かった時代とその背景
私の任官当時の大阪所長は瀧華聡之さん(現在は大津地裁所長)でしたが、この方は、「できるだけ丁寧に説示してあげるように」というスタンスで、裁決書も相対的に長くなる傾向にありました。
瀧華さん在任当時のある裁決書で、法令解釈が「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、・・・医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、・・・(医療法1条の2)」からスタートするものがあったのですが、たとえ医業関係の事案とはいえ、国税の審査請求の法令解釈をそんなところから書いていたら、裁決書全体が長くなって然るべきです。
3.裁決書が相対的に短かった時代とその背景
一方、その後の黒野功久さん(現在は高知地裁所長)になって、一転して、法令解釈の厳選傾向に梶が切られます。
黒野さんの個性というよりも、当時の本部所長の畠山稔さん(平成31年2月に東京高裁部総括判事をもって定年退官)の方針と、当時の大阪審判所の法規審査担当であった裁判官出身の審判官の個性の相乗の為せる業かもしれませんが、「どうしても書かなければ判断できないものしか書かないように」という方針になりました。
当時の本部の幹部が大阪審判所に視察に来られたときの講話を聴いていても、「わからない人にはどれだけ丁寧に書いてもわからないのだから、その事案の軍配を挙げるために最低限必要な法令解釈と判断が記載されていれば良い」という思考から、「行政判断である裁決書を、司法判断である判決書(特に最高裁の判決書)にできる限り近づける」取組みが推進されました。
かくて、瀧華さん在任当時と比べてびっくりするくらいに短い裁決書が同じ大阪審判所から出されるようになったのですが、審査請求人に直接応対する立場である担当審判官の立場からすると、「棄却裁決で、請求人の主張に対してこんなに薄い説示では、請求人は絶対に納得してくれないだろう」と思うこともありました。
4.審査請求前置であることの意味
私と部門を共にしたある国税審査官の言葉です。
「以前は、棄却裁決でも丁寧に説示して、『(訴訟に移っても、どう転んでも救済されない事案については)訴訟に上げるだけ無駄』と諦めさせるようにしていた。実際に自分が担当していた棄却の事案でも訴訟に上がらないものが多かった。しかし、最近は、説示をバッサリ削ってしまったがために請求人が納得せず、訴訟に上がってしまうケースが多くなった。審判所という存在があるのに、そのまま訴訟に進んでしまうようなら、国税通則法上で審査請求を前置させる意味がない。上記のような事案についても、請求人の疑問に無料で丁寧に対応してこそ、行政判断としての存在意義があるのに。」
請求人としては、「主文(結論)」が大事で、主文が「棄却」ならば、どれだけ丁寧に「理由」を書いても同じだ、という考え方もあるでしょうが、国税不服審判所は、むしろ「理由」の書きぶりに膨大なエネルギー(≒人件費)を割いており、棄却裁決を「快諾」するのは無理としても、少しでも負けさせる側の納得性が向上するように説示したいというのが、請求人に直接応対する担当審判官の立場からの願いなのです。