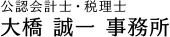1.国税通則法99条の規定
国税不服審判所長は、裁決に当たって、国税庁長官が発した通達による法令の解釈に拘束されないで、独自の解釈により裁決をすることができますし、他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をすることもできます。
しかし、このような場合において、裁決機関の解釈と執行機関の解釈が異なることとなったときに、それをそのまま放置すれば、実務に混乱を来し、納税者に迷惑を及ぼすことになるため、両者の意見の調整を図るため、国税通則法第99条においては、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならないとされています。
そして、審判所長は、審判所長の意見が審査請求人の主張を容認するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、原則として、国税庁長官と共同して、民間の学識経験者からなる国税審議会に対して諮問し、その議決に基づいて裁決しなければならないとされ、民間の公正な意見が国税審議会の議決に反映されて、最終判断として示されることになります。
ここでいう「法令の解釈の先例」とは、判例、学説又は通達、慣行等が未だ確定していない法令の規定について、審判所長がする新たな解釈で、その解釈がその後の解釈の前例となるものをいい、「重要」とは、他の処分を行う際にその解釈が重要な先例となる(当該裁決で示される法解釈が他の法解釈や類似事案に与える影響の大きさ、あるいは、その法解釈の普遍度等を総合勘案して判断する)という意味です。
2.具体的な事案
昭和45年の国税不服審判所創設以来、国税不服審判所本部所長が国税庁長官に意見を申し出た(平成26年の国税通則法改正までは「通知」ではなく「申出」とされていました)事件は9件あります。
第三者的に眺めると「50年間でたった9件しかない」という意見が生じるところですが、審査請求事件の多くは事実認定に関するものであり、また、時代の変化に応じ、国税庁においても通達の整備や改正が行われていることもあって、国税不服審判所としては、一概に申出(通知)の件数が少ないとは評価していないようです。
❶破産会社について仮装経理に基づく減額更正に伴う過納金を即時還付することとした事例(裁決日:昭和46年9月27日)
❷被相続人が外国人である場合の共同相続人の国税の納付義務の承継額は、被相続人の本国法による相続分により計算すべきであるとした事例(昭和47年11月1日)
❸外国人の役員及び使用人に支給した休暇帰国のための旅費は、業務上必要な旅費に当たるとして、賞与と認定した原処分を取り消した事例(昭和49年3月12日)
❹土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その上地の取得に要した借入金の利子は、当該土地の取得費に算入するとした事例(昭和54年9月20日)
❺土地取得後これを利用することなく譲渡した場合には、その土地の取得に要した借入金の利子及び借入金担保のための抵当権設定費用等は、当該土地の取得費に算入するとした事例(昭和54年9月27日)
❻相続により取得した定期預金の評価上、既経過利子の額の算出については、解約利率により算出した額から、源泉徴収による所得税相当額を控除すべきであるとした事例(昭和55年12月1日)
❼既存住宅の共有持分の追加取得は、租税特別措置法第41条(住宅の取得をした場合の所得税額の特別控除)第1項に規定する「既存住宅の取得」に当たるとした事例(平成2年6月25日)
❽代償分割により取得した代償金について相続税の課税価格に算入すべき価額は、代償分割時における代償財産の通常取引される価額と相続税評価額の比により圧縮するのが相当であるとした事例(平成3年4月30日)
❾住宅の共有持分を追加取得したことは、租税特別措置法施行令第26条第2項の「居住の用に供する家屋を2以上有する場合」には該当しないとした事例(平成21年2月20日)
この9件は、重要な先例となると認められる事件が8件、国税庁長官通達と異なる解釈と認められる事件が1件となっており、また、この9件は、いずれも請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官も国税不服審判所長の意見を相当と認めたため、国税審議会に諮ることなく裁決されています。
そうすると、前述で「民間の公正な意見が国税審議会の議決に反映されて」と記述したものの、実際には国税審議会に至る前の国税庁内部で結論を得ていることになります。
3.これからも国税審議会を経ることはない
私は、将来的にも国税審議会までもつれるケースは出て来ないと考えています。
それは、国税審議会に判断が委ねられるということは、国税庁長官(国税庁No.1)と国税不服審判所長(国税庁No.2)の意見が国税庁内ですり合わせできなかったことを自白し、かつ、同審議会の議決によっていずれか一方の意見が排斥される(恥をかく)ことを意味します。
官僚的組織においては、たとえ内部に意見の対立はあったとしても、対外的には1枚岩を演出することになり、組織内部でいずれか一方が折れることによって決着を見ることになるのが通常です。
これまでの9件は、国税庁長官が、格下であるも判断機関である国税不服審判所の意見を尊重することで、「審判所が有効に機能していること」及び「国税庁の度量の大きさ」をアピールしているという側面もないわけではないのでしょう。
それでも、50年間でたった9件なのですが・・・。