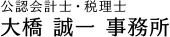1.任官した瞬間から年間20日換算で付与
労働基準法に「年次有給休暇(いわゆる「有休」)」が規定され、民間企業はこれに服していますが、公務員の世界では「年次休暇」が人事院規則に規定されています。
民間が「有休」と略するのに対し、公務は「年休」と略することが多く、私が国税審判官に任官された当時は周りの税務職員のこの言葉の違いにいささか違和感を覚えたものです。
民間の有休は、原則として入社半年経過後に年間10日付与され、その後、11日、12日、14日、16日、18日と増加して、その後は20日付与で固定される仕組みになっていますが、実際には余程の優良企業でない限り、満足に消化できない(会計事務所従業員は特に)というのが実情でしょう。
一方、公務の年休はいきなり年間20日換算(基準は年末)で任官した瞬間から付与されます。
例えば、4月1日任官の場合はその年の年末までに15日、7月10日任官の場合はその年の年末までに10日付与されますが、民間が入社半年経過まで付与しなくても法令違反ではないことと比較すると、かなり配慮されていることがわかります。
私の後輩の国税審判官が7月10日に任官辞令を受けた後、挨拶しようと彼の所属する審判部に赴くと彼の姿はなく、周りの審査官に聞くと、「公務員宿舎の入寮手続のために時間年休を取得されました」と言われました。
ちなみに、民間出身の国税審判官は7月9日が任期満了(すなわち定年)であり、この場合には、その年の1月1日に(20日ではなく)12日が付与されることになります。
2.時間年休による残日数計算の煩雑さ
最近では、民間の有休においても「1時間単位」の取得が可能になるような改正が図られましたが、公務の年休は以前から1時間単位で取得することができます。
しかし、国家公務員の現在の1日の所定労働時間は7時間45分であり、時間年休を取得すると次のような計算を必要とします。
例えば、「20日」から3時間、次に4時間年休を取得すると残が「19日0時間45分」となりますが、そこから1時間取得する場合、残が「18日7時間30分」となるところ、こんな煩雑な計算を本人が紙ベースの「休暇簿」で申請し、上長(国税審判官の場合は部長審判官)承認後、管理課総務係が検算して人事管理を行っているのです。
3.1月末の辞職の例
ある税務職員が1月31日付けで辞職したことがありましたが、彼は年休の残日数が30日程度あったそうです。
その職員が「1月31日付けで辞職した」と聞いたとき、私はとっさに「年を跨いで新たに年休をチャージしたんだな」と察しました。
前述のとおり、公務の年休は年末基準で1月1日に新たに20日加算されるところ、辞職する1月は正月休みや成人の日の祝日もありますので、新たに付与された20日を消化することができます。
そうすると、もともとの残日数である30日は、辞職する年の前年にまるまる充てることができ、彼の場合は、おそらく11月中旬から年休の消化ができたものと思われます。
そして、12月10日支給の期末勤勉手当(いわゆる賞与)も受給して辞職したということが推察されます。
人事管理に詳しいOB税理士に言わせれば、「年末までの辞職であれば、定期異動まで半年あることから『補正人事(補充人事)』が行われたはずで、それは昇格人事であることから異動対象者にもメリットがある。しかし、1月に入ってしまうと定期異動まで半年を切るため、組織の要職でなければ補正人事が行われず、残った職員でその穴を埋めなければならない。年休付与のメリットがあったとしても、その時期の辞職はちょっといただけない・・・。」というお話でしたが、こういった「辞め方の作法」については公務に限らず民間でもいえることかもしれません。